- トップ
- > 国立成育医療研究センターについて
- > 主な取り組み
- > こどもの医療被ばくを考えるサイト PIJON
- > 小児画像検査について
- > 前準備
前準備
小児におけるCT検査の前準備
最良のCT検査を行うにあたって事前に十分な患者情報を得ておくことは、CT撮影技術の最適化と同様に重要です。取り組むべき準備は、大きく分けて次の3つが挙げられます1)。
- 小児および両親に対する(検査環境を加味した)精神的な準備
- 鎮静および麻酔の必要性に関する準備
- 造影CTに関する準備
精神的準備と鎮静の必要性
検査前の準備として、次のような事項が必要です。
- 小児の年齢や興味に関する情報および、両親へのCT検査における情報の準備(例えば書面での説明、検査シミュレーション、検査説明、遊戯療法に関してなど)
- 小児の気を引けるようなものを用意する
- 両親が検査前、検査後に小児と一緒にいること
- 検査室を小児が落ち着く環境にすること
- 絵や色を付けたカーテンをガントリーにかける
- 天井や壁に絵や色を付けたり、プロジェクションをする
- 子どもの好きな音楽や動画を流す
当センターでは、CTガントリーに子どもたちの好きなドーナツのペインティングが施されています。
こうした取り組みを行うことで、鎮静剤や麻酔薬を用いなくてもCT検査を円滑に行える確率は上がります。一般的に5歳以上では、指示をすれば鎮静や麻酔を用いなくてもCT検査を行えます1)。しかし、鎮静や麻酔の必要性は、検査の種類や小児の発達、精神状況、検査意義などによっても左右されるため考慮が必要です。鎮静薬使用については個別に小児科受け持ち医と事前相談しておきましょう。
また施設によってはChild Life Specialist (CLS)という認定資格を持つ専門職がいて、CT検査の時、子どもが少しでも安心できるように寄り添います。子どもが孤独にならないように、子どもの緊張や不安、苦痛を軽減できるように支援します。

国立成育医療研究センター CT室
小児造影CTに関して
造影剤注入はインジェクター?手押し?
経静脈的な造影剤注入は、用手注入(手押し)ではなく造影剤自動注入器(以下インジェクター)を用いるのが理想です。そのためカニューレは可能な限り肘正中静脈に穿刺するべきです(ただし子どもの年齢にも左右され、小児科受け持ち医に相談しましょう)。
CVL(Central Venous Line)やポートからの造影は可能ではあります。しかし、それらの最大許容圧はおよそ30-40Psi程度であるのに対し、インジェクターでの最小設定圧は50Psi程度であるため1)、CVLを用いる際は手押しでの造影を行うべきです2)。手押しの場合のCVLの破損率はわずか0.3%と報告されています2)。とはいえ、近年の文献や日常診療の経験より、大方問題ないとの報告もあります3)。Rigsbyらはインジェクターを使用する場合は25psi以下に注入圧を制限し、体重30㎏以下の場合に限り行うよう推奨しています3)。近年、注入圧に耐えられるパワーポート(Power PICC, BARD社など)が使用可能となり、安全にインジェクターを用いて静脈からの造影を行えるようになってきました。
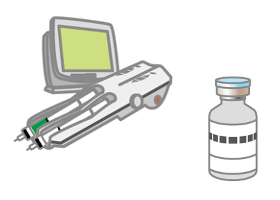
注入量は?
一般的な造影剤としては、非イオン性で低浸透圧な組成であり、240-400 mg I/mlの濃度で用いられる(300 mg I/mlが最も用いられています)。小児において、過度な肥満や注入レートが低い場合を除いては370-400 mg I/ml程度の高濃度造影剤を用いる必要はないと考えます。造影剤注入量は、一般的に2.0 ml/kg (300 mg I/ml)が用いられ、600 mg I/kgとなります。しかし、新生児や乳児は、成人と比較して細胞外液量の割合が多いため、体重当たりのヨード量が多く必要となることも考えられます。注入量については、体重が3 kg以下の場合、2.0 ml/kgでは造影剤注入容量が少なく、インジェクターによる1 mLの注入誤差が与える影響が大きくなるため、造影剤を生理食塩水で希釈して使用している施設もあります(1.5 kg以下では2倍希釈、3 kg以下では1.5倍希釈)。また、造影用の耐圧チューブ(インジェクターチューブ)を用いて接続した場合は内容量が約4.0 mlであるため、体重が3 kg以下の場合は希釈して注入量を増す要があります。
12歳以下の小児において、造影剤注入速度は通常は1.0~2.0 ml/s程度で十分です。以下に一般的な注入条件を示します。
検査目的と注入量の目安(米国小児放射線学会(SPR)のサーベイの結果4))を表1に示します。
注入スピードは?Scan delayは?
造影剤の注入スピードは造影用の静脈ルートのゲージ数(太さ)に依存します。また当然ながら静脈ルートのゲージ数は患児の年齢により異なります。新生児や乳児ではより細いルート(24ゲージ)になります。また心臓CTやCTアンギオが必要な場合は太いルートの確保を主治医に依頼することになります。
造影剤の急速注入には耐圧チューブの用意やロック付きのコネクターが必要であり、これらがない場合は造影剤のコネクター連結部で造影剤の漏れや留置針とチューブ連結部での漏れなどが起こるため注意が必要です。検査目的別の造影CTにおける造影剤注入量の目安を表1に、一般的な静脈ルートゲージ数と造影剤注入速度の推奨を表2、造影CT撮影開始のタイミングの例を表3に示します。
表1 検査目的別の造影CTにおける造影剤注入量の目安4)
| 造影CTの目的 | 注入スピードの目安 |
|---|---|
| CTアンギオ以外の通常の頭部、頸部、胸部、腹部CT | 1.0 ~ 2.0ml/秒 |
| 腹部、四肢のCT angiography | 2.0 ~ 4.0ml/秒 |
| 頭部、頸部のCT angiography | 2.0 ~ 4.0ml/秒 |
| 胸部のCT angiography | 2.5 ~ 4.0ml/秒 |
表2 静脈ルートゲージ数と造影剤注入速度の例(最大値)
| 静脈ルートゲージ数 | 注入量 (国立成育医療研究センターCT室) |
注入量 (米国小児放射線学会のサーベイ5)) |
|---|---|---|
| 24ゲージ | 0.8 cc/秒以下 | 1.0 cc/秒以下 |
| 22ゲージ | 2.0 cc/秒以下 | 2.5 cc/秒以下 |
| 20ゲージ | 3.0 cc/秒以下 | 4.0 cc/秒以下 |
| 18ゲージ | 5.0 cc/秒以下 | 5.0 cc/秒以下 |
表3 造影CT撮影開始のタイミングの例
| Indication | Scan delay |
|---|---|
| 頭部 造影ルーチンCT(腫瘤、 転移病変検索など) | 注入開始後 60秒1)~ 200秒5) |
| CTアンギオ(血管奇形、外傷、術前など) | Bolus tracking technique delay: BT150+6 s1) |
| 腹部 造影ルーチンCT(実質相、単相撮影) | 注入開始後60秒、遅くとも注入終了後10~15秒以内6)(年齢、体重、目的により異なる。年長児は遅めに設定) |
まとめ
本稿は、小児CT撮影の被ばく低減テクニック以外の実践的かつ総論的な手法、特に造影剤の投与用法を記載しました。小児病院や大学病院で数多くの小児CT撮影を行っている施設では、既に各施設でのルーチンの撮影方法が確立されている場合が多いと思います。一方、小児のCT件数がそれほど多くない施設では造影剤の注入やScan delayの設定で迷う状況も多くあると思います。そのような場合に本稿が参考になれば幸いです。
参考文献
- Nievelstein RA, van Dam IM, van der Molen AJ. Multidetector CT in children: current concepts and dose reduction strategies. Pediatr Radiol. 2010 Aug;40(8):1324-44.
- Donnelly LF, et al. Is Hand Injection of Central Venous Catheters for Contrast-Enhanced CT Safe in Children? AJR 2007; 189:1530-1532
- Ringsby CK, et al. Safety and Efficacy of PressureLimited Power Injection of Iodinated Contrast Medium Through Central Lines in Children. AJR 2007; 188:726-732
- Callahan JM, et al. Practice patterns for the use of iodinated IV contrast media for pediatric CT studies: A Survey of the Society for Pediatric Radiology. AJR 2014; 202:872-879
- 日本放射線技術学会撮影部会:X線CT撮影における標準化〜GALACTIC〜(改訂2版) 京都:日本放射線技術学会,2015
- Siegel MJ (2008) Practical CT techniques. In: Siegel MJ (ed): Pediatric Body CT, 2nd edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia pp 1-32
宮嵜 治(国立成育医療研究センター 放射線診療部 診療部長)



